第7次エネルギー基本計画の変遷と最新トレンド:企業が注目すべきポイント徹底解説
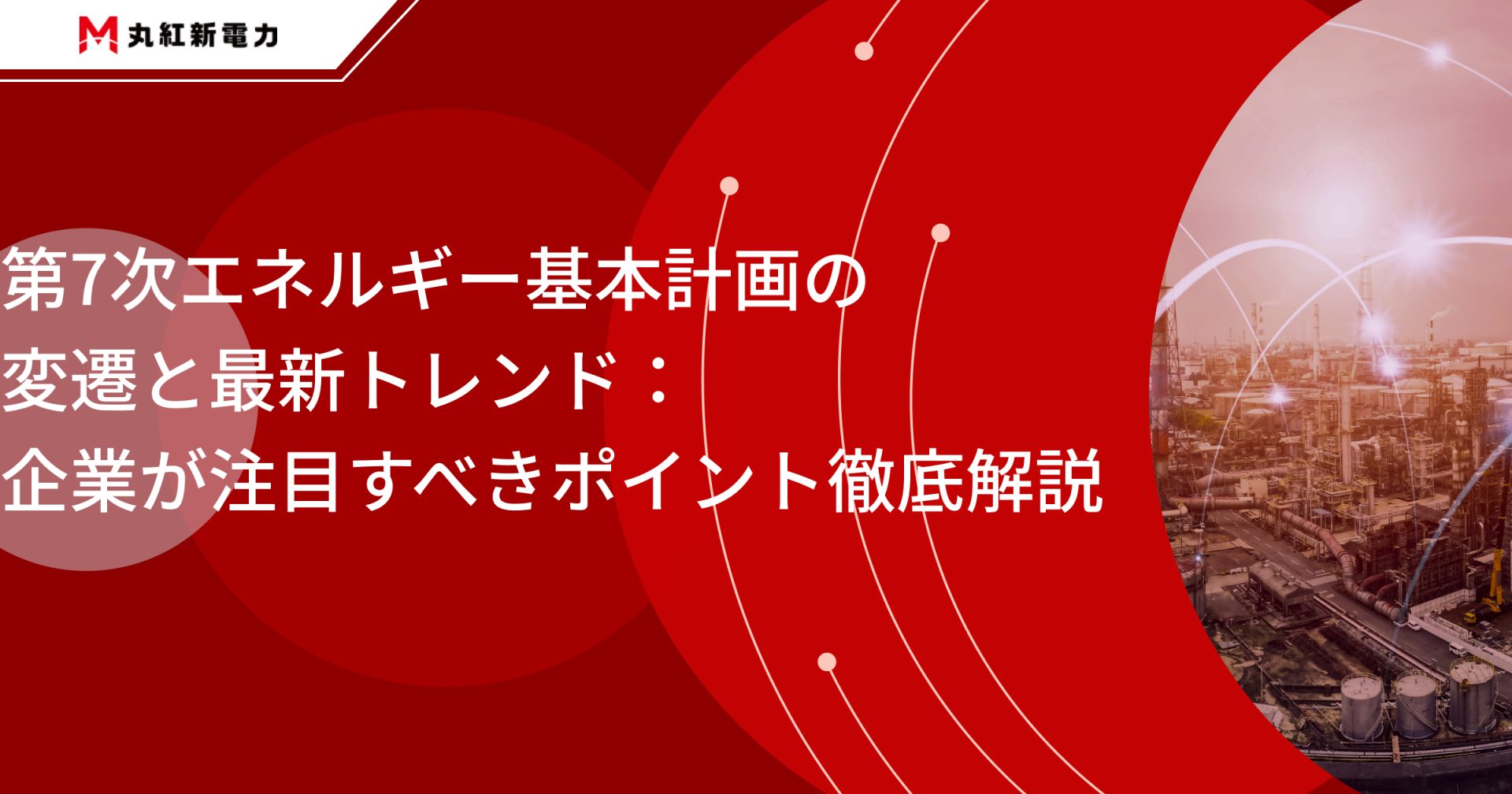
エネルギーは現代社会の基盤を支える重要な要素であり、企業活動にも大きな影響を与えます。日本政府が策定する「エネルギー基本計画」は、エネルギー需給の安定化や環境への配慮、市場原理の活用などを柱とし、持続可能なエネルギー政策を推進するための指針となっています。今回、最新の第7次エネルギー基本計画が発表され、前回からの大きな変更点や現在のエネルギー市場のトレンドが注目されています。本コラムでは、第7次エネルギー基本計画の概要とその変遷、最新トレンドを踏まえ、企業が押さえるべき重要ポイントについて詳しく解説します。
>> 【法人のお客様向け】再生可能エネルギー由来の電力を組み合わせた環境配慮型電力プラン
目次
エネルギー基本計画とは?

エネルギー基本計画は、日本のエネルギー需給に関する長期的かつ総合的な施策を計画的に推進するための国家戦略です。エネルギー政策基本法に基づき、安定したエネルギー供給、環境への適合、市場原理の活用を基本方針として策定されています。これにより、エネルギーの安定供給と持続可能な社会の実現を目指しています。
第7次エネルギー基本計画の概要

第7次エネルギー基本計画は、令和7年2月に資源エネルギー庁より公布されました。この計画は、「GX2040ビジョン」や「地球温暖化対策計画」と一体的に活用され、日本のエネルギー政策の将来像を示すものとなっています。主な目標として、エネルギーの安定供給を確保しつつ、カーボンニュートラルを達成することが掲げられています。
表1:第7次エネルギー基本計画の主要目標
| 目標 | 詳細 |
|---|---|
| 安定供給の確保 | 多様なエネルギー源の確保と供給体制の強化 |
| 環境への適合 | 再生可能エネルギーの拡充と温室効果ガス削減 |
| 市場原理の活用 | エネルギー市場の自由化と競争促進 |
前回からの変更点

第7次エネルギー基本計画では、前回の計画からいくつかの重要な変更点が見られます。
- 再生可能エネルギーのさらなる拡充
- 再生可能エネルギーの比率を従来の目標よりも高く設定し、2030年までに再エネ比率を50%以上に引き上げる方針が明確化されています。これにより、企業は自社製品のブランド力強化や取引先の拡充といったメリットを享受できます。
- 原子力発電の役割の見直し
- 原子力発電の安全性強化とともに、エネルギーミックスにおける原子力の役割を再評価し、持続可能な運用を推進します。これにより、エネルギー供給の安定性がさらに高まります。
- エネルギー貯蔵技術の重要性強調
- エネルギーシステムの安定化のため、蓄電池や水素エネルギーなどの貯蔵技術の研究開発を強化します。これにより、再生可能エネルギーの変動性を補完し、安定供給が可能となります。
- デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進
- エネルギーマネジメントシステムの高度化を図り、AIやIoTを活用した効率的なエネルギー運用を目指すとともに、企業の省エネルギー取り組みを支援します。
- 中小企業への支援強化
- 中小企業にとってのGX(グリーントランスフォーメーション)の取り組みが強調され、省エネルギーを契機とした脱炭素への第一歩としての支援が充実されます。規制と支援を一体的に進めることで、中小企業や家庭の脱炭素化を促進します。
▶下記の記事も併せて参考にご覧ください。
・GXとは?:持続可能な成長への道筋
最近のエネルギートレンド

エネルギー業界では、技術革新と市場の変化が急速に進行しています。以下に最近の主要なトレンドを紹介します。
再生可能エネルギーの急速な拡大
太陽光、風力、水力などの再生可能エネルギーは、コスト低減と技術進歩により急速に拡大しています。特に、洋上風力発電や大型太陽光発電所の建設が進展し、供給能力の向上が見込まれます。また、バイオマスエネルギーや地熱発電など、多様な再生可能エネルギーの導入が進んでいます。
エネルギー貯蔵技術の進化
再生可能エネルギーの変動性を補完するための蓄電池技術や、水素エネルギーの利用が注目されています。これにより、エネルギーの安定供給と効率的な利用が可能となります。特に、水素エネルギーは産業用途や輸送分野での活用が進んでおり、CCUS(Carbon Capture, Utilization, and Storage)技術との組み合わせでさらなる脱炭素化が期待されています。
デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展
AIやビッグデータを活用したエネルギーマネジメントが進展し、エネルギーの需要予測や供給調整が高度化しています。これにより、エネルギー効率の向上とコスト削減が実現されています。さらに、スマートグリッドの普及により、消費者と供給者の双方向のエネルギーフローが可能となり、エネルギーの最適化が図られています。
企業が抑えるべきポイント

エネルギー基本計画の変更点や最新トレンドを踏まえ、企業が注目すべきポイントは以下の通りです。
エネルギーコストの最適化
企業にとってエネルギーコストは重要な経営要素です。第7次エネルギー基本計画に基づくエネルギー供給の多様化により、企業は電力の供給先や料金プランを見直し、コスト最適化を図ることが重要です。具体的には、新電力の活用や長期固定価格契約の検討が有効です。また、省エネルギー技術の導入や設備の効率化を通じて、エネルギー消費の削減も重要です。
再生可能エネルギーの活用
再生可能エネルギーの導入は、環境負荷の低減のみならず、長期的なコスト削減にも繋がります。自社での太陽光発電設備の設置や、再エネ電力の購入を積極的に検討することで、エネルギーコストの安定化を図ることが可能です。さらに、中小企業にとっては、省エネと脱炭素化を同時に進めることで、ブランド力の強化や新たな取引先の獲得が期待できます。
エネルギーマネジメントの強化
AIやIoTを活用したエネルギーマネジメントシステムの導入は、エネルギー使用の効率化とコスト削減に大きく寄与します。リアルタイムでのエネルギー使用状況の把握や、需要予測に基づく最適なエネルギー供給の管理が求められます。加えて、エネルギー貯蔵技術の導入や、スマートメーターの活用により、エネルギーの最適化と省エネが実現します。
表2:企業が導入すべきエネルギーマネジメント手法
| 手法 | 詳細 | 効果 |
|---|---|---|
| AIによる需要予測 | 過去データを基に将来のエネルギー需要を予測 | エネルギー供給の最適化 |
| IoTデバイスの導入 | 各設備にセンサーを設置し、エネルギー使用をリアルタイムで監視 | 無駄なエネルギー使用の削減 |
| エネルギー管理ソフトの活用 | エネルギー消費を可視化し、効率的な運用を支援 | コスト削減と効率向上 |
今後の展望と企業への影響

第7次エネルギー基本計画は、エネルギー市場に大きな影響を与えるとともに、企業のエネルギー戦略にも重要な指針を提供します。以下の点が今後の展望として挙げられます。
- エネルギー供給の多様化:再生可能エネルギーの割合が増加し、供給元が多様化することで、企業は柔軟なエネルギー調達が可能となります。これにより、エネルギー価格の変動リスクを軽減し、安定した供給を確保できます。
- 技術革新の推進:エネルギー貯蔵技術やスマートグリッドの普及により、エネルギーの効率的な利用が可能となり、企業の運用効率が向上します。さらに、CCUS技術の進展により、炭素排出量の削減が加速します。
- 環境規制の強化:カーボンニュートラル達成に向けた規制が強化される中、企業は環境に配慮したエネルギー使用を求められるでしょう。これに対応するため、省エネ投資や再生可能エネルギーの導入が不可欠となります。
また、脱炭素化に向けた取り組みは、エネルギーのコスト削減やブランド価値の向上にも繋がります。特に中小企業にとっては、省エネルギーを契機とした脱炭素化が、持続可能な成長戦略の一環として重要です。支援と規制を一体的に進めることで、企業は効率的かつ効果的に脱炭素化を推進できます。
まとめ

第7次エネルギー基本計画は、エネルギーの安定供給と持続可能な社会の実現を目指す重要な国家戦略です。再生可能エネルギーの拡充やエネルギーマネジメントの強化といった変更点は、企業にとっても大きな影響を与えます。企業はこれらの変化を踏まえ、エネルギーコストの最適化や再生可能エネルギーの活用、エネルギーマネジメントの強化を図ることで、持続可能なビジネス運営を実現することが求められます。特に、中小企業に対する支援強化や脱炭素化への第一歩としての省エネ取り組みは、企業の競争力向上に直結します。エネルギー基本計画の動向を常に把握し、柔軟な対応を行うことが、今後の企業の持続的成長と競争力向上に繋がるでしょう。














