電気料金に隠れる託送料金相当額とは?企業が知るべき料金構成と最新制度の影響
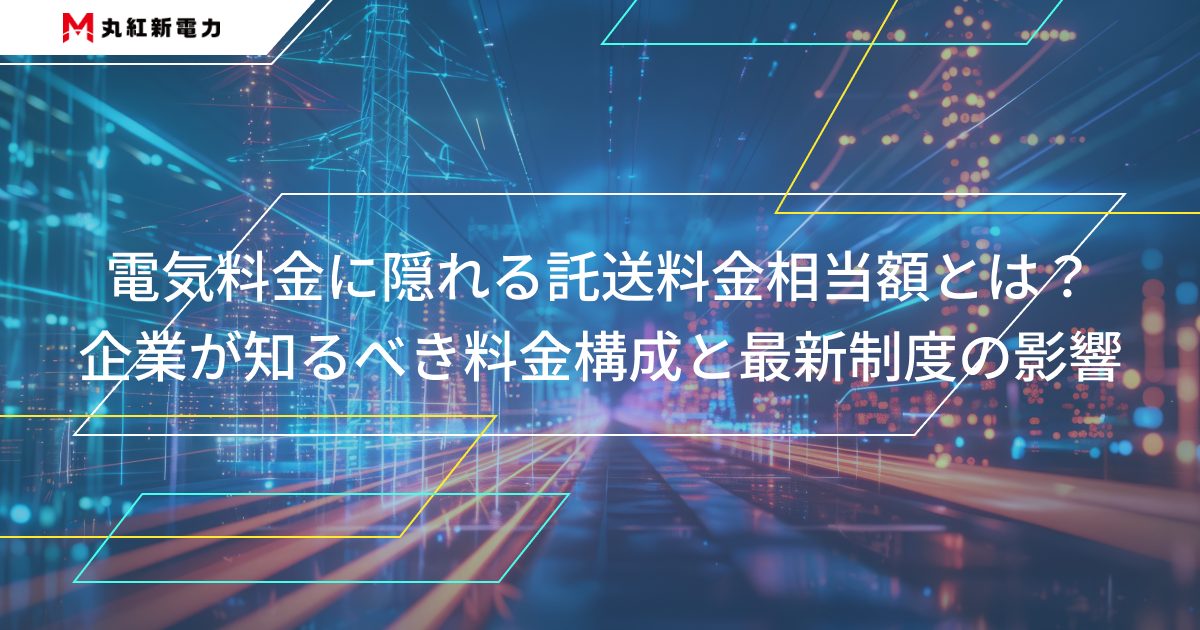
企業活動において電力コストは無視できない経費の一つです。しかし、電気料金の明細を詳しく見ると「託送料金相当額」として内在する項目が存在し、これが料金全体に大きな影響を与えています。本コラムでは、託送料金の概要と料金構成、最新の制度変更について解説し、企業が電力メニューを選択する際に考慮すべきポイントを明らかにします。
>> 【法人のお客様向け】再生可能エネルギー由来の電力を組み合わせた環境配慮型電力プラン
目次
託送料金の概要

託送料金とは?
託送料金とは、一般送配電事業者が発電所から需要家の施設まで電力を安定的かつ安全に供給するために必要な費用を賄うための料金です。具体的には、送電線や変電設備の維持管理費、設備投資費用、運営費用などが含まれます。需要家は電力会社を通じて電気を購入する際、実際の電力使用量に加え、この託送料金を送配電事業者に支払っています。企業の電気料金全体の約30%を占めるこの託送料金相当額は、安定した電力供給の基盤を支える重要な要素です。
託送料金の料金構成:基本料金と従量料金
託送料金の構成は、一般的に基本料金と従量料金の2つの要素で構成されています:
- 基本料金:これは契約電力(契約容量)に基づいて設定され、電気を使用しなくても支払う固定費用です。需要家の設備容量に応じて設定され、設備投資や送配電設備の維持管理費用をカバーします。
- 従量料金:これは実際に使用した電力量(kWh)に課金される料金です。
最新制度の影響

近年、電力業界では料金制度に大きな変化が見られます。特に2023年度から始まったレベニューキャップ制度と、2024年度から導入された発電側課金制度は、企業の電気料金に直接的な影響を及ぼしています。これらの制度改革は、電力市場の透明性向上とコスト効率化を目的としています。
レベニューキャップ制度(2023年度開始)
レベニューキャップ制度は、一般送配電事業者の収益を一定の上限に抑えることで、過剰な料金上昇を防ぐ制度です。具体的には、送配電事業者の年間収益が事前に設定されたキャップを超えないように規制します。この制度の導入により、送配電事業者は効率的な運営が求められ、無駄なコストを削減するインセンティブが高まります。一方で、需要家にとっては安定した託送料金を維持しやすくなりますが、過度なコスト削減がサービス品質に影響を与えないよう監視が必要です。
発電側課金制度の導入(2024年度から)
2024年度からは、発電者も託送料金の一部を負担する「発電側課金制度」が導入されています。これまで需要家が全て負担していた託送料金の一部を、発電事業者が負担することで、需要家の負担軽減を図ります。この制度変更により、企業は電気料金の透明性が高まり、コストの見直しがしやすくなります。具体的には、発電事業者が効率的な発電方法を採用する動機づけとなり、結果として全体の電力コストが低減する可能性があります。
| 制度名 | 主な目的 | 企業側メリット |
|---|---|---|
| レベニューキャップ制度 | 託送料金の過度な上昇を抑制することで、電力市場の透明性を向上 | 託送料金の安定性向上と予算管理が容易になる |
| 発電側課金制度 | 発電者にも送配電コストを一部分担させ、需要家の負担を軽減 | 需要家の電気料金が透明化・コスト削減が可能 |
託送料金相当額の理解と電力メニュー選択
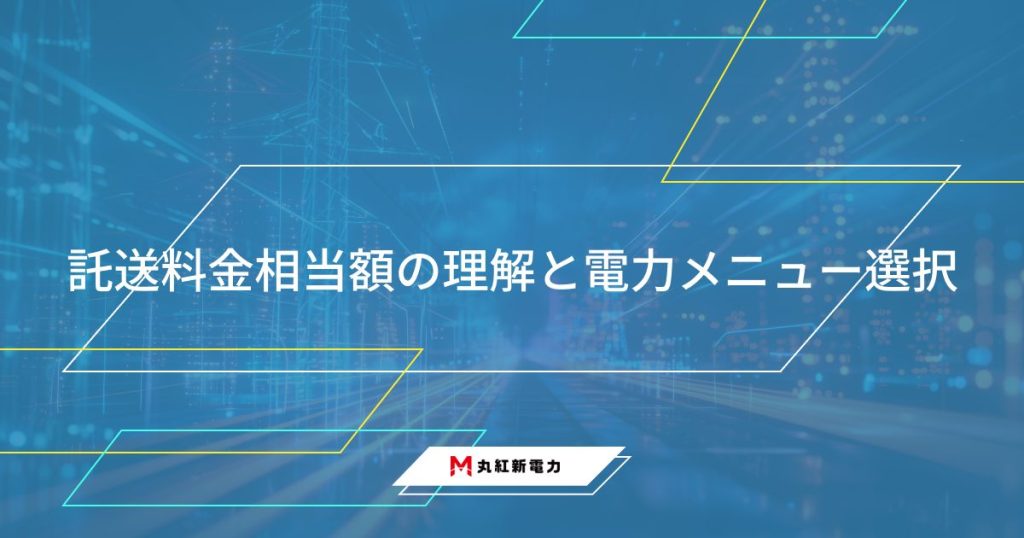
電力メニュー選択時のポイント
託送料金相当額を理解した上で、企業が電力メニューを選択する際のポイントは以下の通りです:
- 料金構成の確認:基本料金と従量料金のバランスを理解し、自社の電力使用パターンに最適なプランを選ぶことが重要です。例えば、平常時に大量の電力を使用する企業は、基本料金が高いプランよりも従量料金が低いプランを選択する方がコスト削減につながる場合があります。
- 複数社の比較:異なる電気事業者の料金プランを比較し、最適なコストパフォーマンスを追求することが求められます。電力自由化により、多くの新規参入企業が多様なプランを提供しているため、自社のニーズに最も適したプランを選ぶためには、詳細な比較検討が必要です。
- 付加価値サービスの検討:再生可能エネルギーの利用やエネルギーマネジメントサービスなど、料金以外の付加価値サービスも考慮することが重要です。例えば、環境意識の高い企業では、再生可能エネルギーを利用するプランを選択することで、企業イメージの向上や社会的責任の履行につながります。
具体的な電力選択の事例
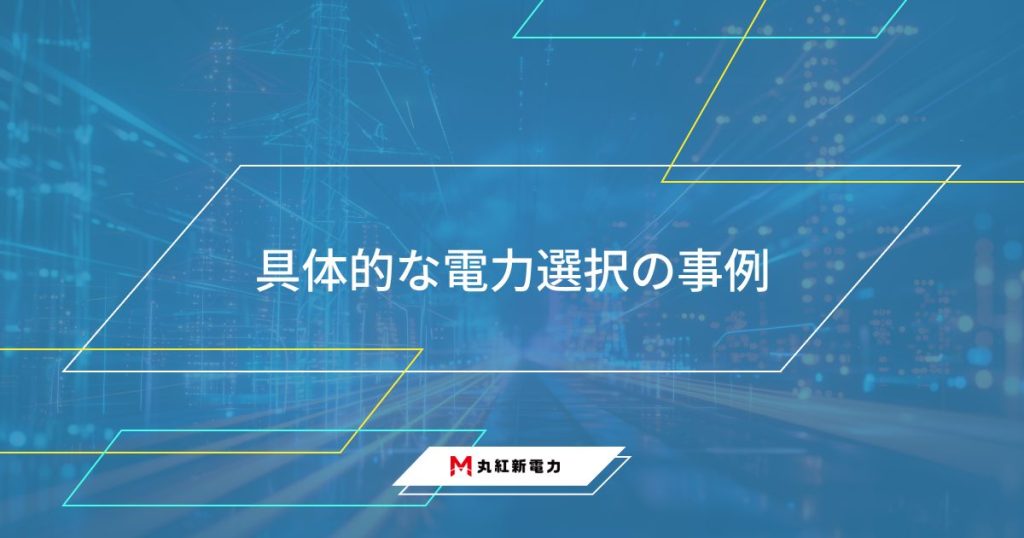
企業の電力使用パターン別最適プラン
企業の電力使用パターンは業種や運営形態によって異なります。例えば、製造業では設備稼働時に大量の電力を消費する一方、オフィスビルでは平常時の電力消費が中心となります。それぞれのパターンに応じた最適な電力プランを選択することで、コスト削減が可能です。
- 製造業の場合:ピーク時の大量電力消費に対応するため、従量料金が低いプランを選択することが有効です。また、需要調整契約を活用して、ピーク時の電力使用を抑えることで追加料金を削減する方法もあります。例えば、自動車製造業では夜間稼働を活用し、コスト削減に成功した事例があります。企業は、電力使用パターンに応じたプラン選択をシミュレーションすることで、どのプランが最も効果的かを慎重に検討することが重要です。
▶下記記事も併せてご確認ください
- オフィスビルの場合:基本料金が比較的低めで、従量料金が中程度のプランを選択することで、平常時の電力コストを抑えることが可能です。昼間の電力消費が多い場合には、時間帯別料金プランを活用することで、効率的な電力使用を実現できます。例えば、IT企業のオフィスでは、昼間の太陽光発電を活用した電力供給を組み合わせることで、電力コストをさらに削減することができます。
▶下記記事も併せてご確認ください
法人企業向け再生可能エネルギー導入ガイド:持続可能なビジネスへの第一歩
再生可能エネルギーの活用例
再生可能エネルギーを活用することで、環境負荷の軽減だけでなく、長期的なコスト削減も期待できます。例えば、太陽光発電を導入することで、自社で発電した電力を使用し、余剰電力を売電することで収益を得ることが可能です。また、再生可能エネルギーを利用したプランを選択することで、託送料金の一部を固定化し、電力コストの安定化を図ることができます。
▶下記記事も併せてご確認ください。
企業向け太陽光発電の最新トレンドと導入メリット|コスト削減と環境貢献を実現
【まとめ】

託送料金相当額は、企業の電気料金において約30%を占める重要な要素です。2023年度からのレベニューキャップ制度や、2024年度からの発電側課金制度の導入により、託送料金の負担構造は大きく変わりつつあります。企業が効率的かつコスト効果の高い電力メニューを選択するためには、これらの制度変更を含めた料金構成の理解が不可欠です。
需要家は、自社の電力使用状況を詳細に分析し、複数の電気事業者のプランを比較検討することで、最適な電力供給を実現しましょう。託送料金相当額の正確な把握は、電力コスト削減への第一歩となります。また、最新の制度変更を把握し、柔軟に対応することで、将来的な電力コストの変動にも対応可能です。企業は、電力コストの最適化を図るために、専門家のアドバイスを受けることも一つの有効な手段です。
最終的に、電力料金の透明性を高め、効率的なコスト管理を行うことで、企業の競争力強化につながることを目指しましょう。














