脱炭素経営の意味・メリットや取組みの流れをわかりやすく解説
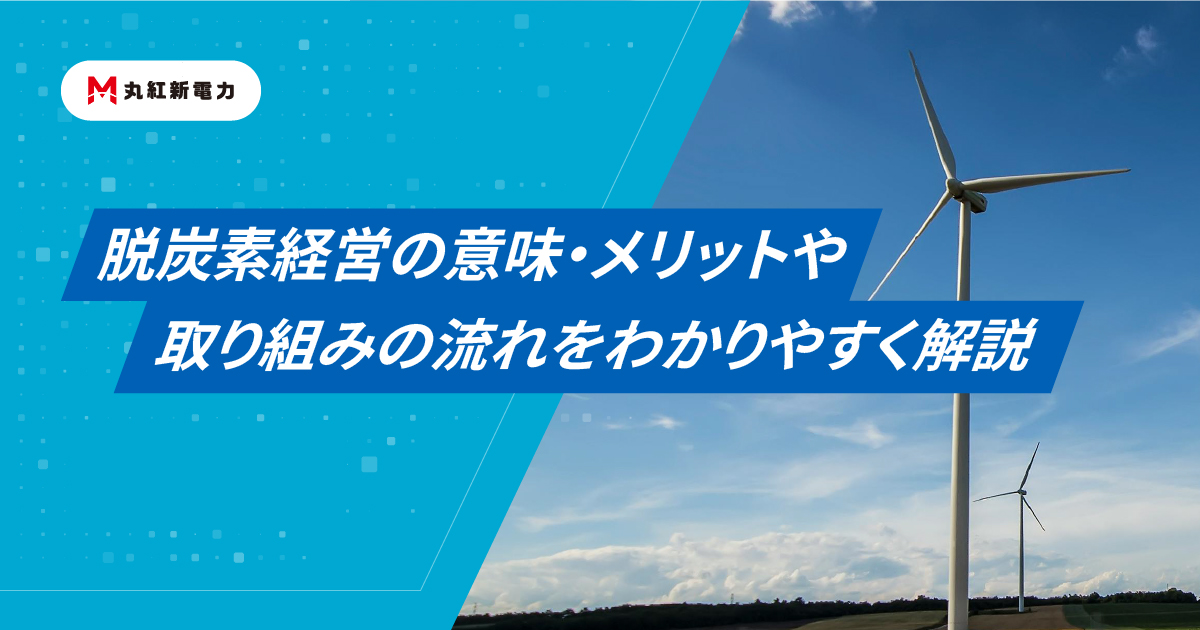
2023年は日本でも災害級と言われる猛暑が起きるなど、記録的な年となりました[1]。しかし気候変動の影響は、豪雨や猛暑のリスクだけではありません。気候の変化が長期にわたって続く場合、温暖化対策税の引き上げやエネルギー価格高騰に伴う売上原価や販管費の上昇を引き起こし、ビジネス面に大きく影響を与える可能性があります。
そこで注目を集めているのが、経営に「気候変動対策(脱炭素)」の視点を取り入れる脱炭素経営という考え方です。脱炭素経営に事業規模の大小は関係ありません。近年は中小企業の間でも、脱炭素経営の考え方が少しずつ浸透しています。
本記事では、脱炭素経営の意味・メリットや、取組みの流れを中小企業向けに解説します。
>> 【法人のお客様向け】高圧・特別高圧の電力プランはこちら
目次
脱炭素経営の意味
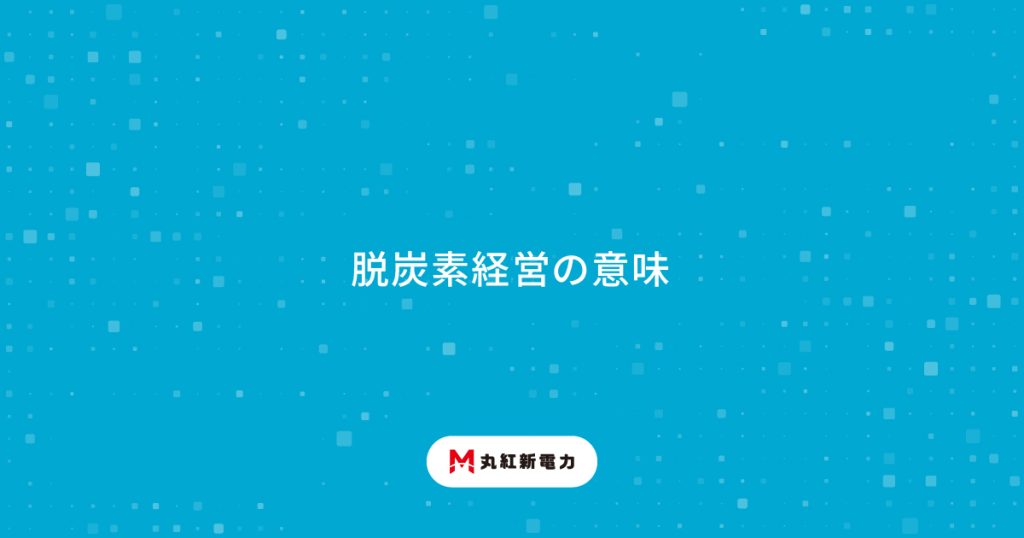
脱炭素経営とは、環境省によると『気候変動対策(≒脱炭素)の視点を織り込んだ企業経営』のことです[2]。脱炭素を単なる環境対策としてではなく、長期的な経営リスクの軽減や、事業を成長させる新たなチャンスという視点で捉え、経営上の重要課題として脱炭素化に取り組むのが脱炭素経営です。
[2]環境省「中小規模事業者向けの脱炭素経営導入ハンドブック」
脱炭素経営が浸透している背景
脱炭素経営というと、「大きな投資が必要なのでは?」「成果が出るまで何十年もかかるのでは?」と懸念する方もいるかもしれません。
しかし、2020年10月に政府が行った「2050年カーボンニュートラル宣言」を一つのきっかけとして、サプライチェーン全体でカーボンニュートラルに向けた動きが広がりました。カーボンニュートラルをはじめとした環境活動は、中小企業にとっても他人事ではありません。脱炭素経営の考え方は大企業だけでなく、サプライチェーンを構成する中小企業の間でも少しずつ浸透しつつあります。
中小企業が脱炭素経営に乗り出す背景にあるのは、新型コロナウィルス感染症の流行や、世界的なエネルギー価格の高騰によって生まれた、経営リスクへの強い危機感です。厳しい事業環境を乗り越えて、競合他社にはない新たな強みを生み出すため、全社を挙げて脱炭素経営に取り組む中小企業が増えています。
脱炭素経営を推進する中小企業のメリット
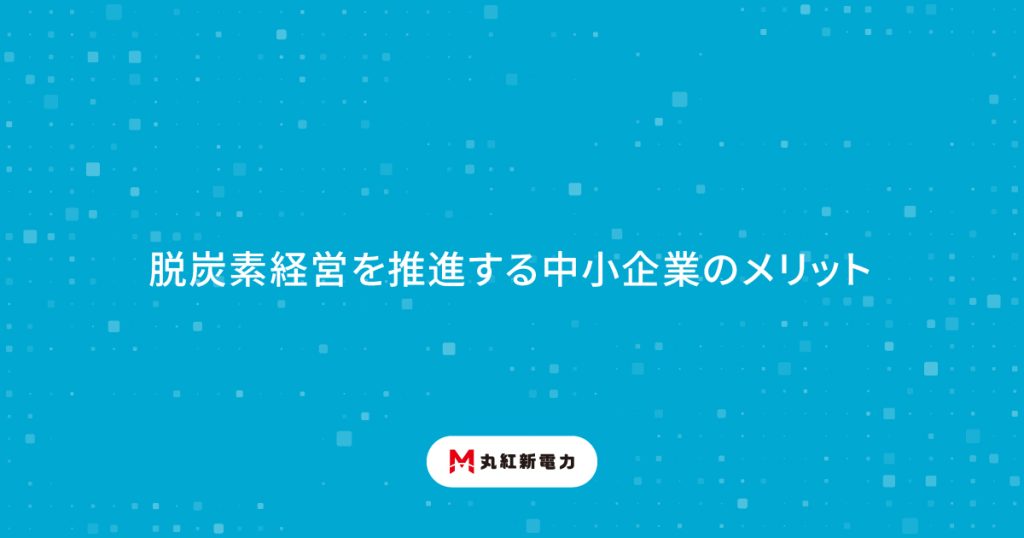
競合他社に先行して脱炭素経営に取り組むことで、中小企業は以下4つのメリットを得られます。
- 優位性を構築できる
- 社会へのアピールにつながる
- 人材採用につながる
- 補助金を活用できる
優位性を構築できる
1つ目のメリットは、競合他社に対する優位性を構築できるという点です。
脱炭素経営に向けた取組みは、まだまだ一般的ではありません。競合他社に先駆けて脱炭素経営を取り入れることで、環境活動に取り組む先進的な企業としてのイメージを確立し、市場競争で優位に立てます。
社会へのアピールにつながる
2つ目のメリットは、社会へのアピールにつながるという点です。
脱炭素経営に向けた取組みを、SNSやWebサイト、プレスリリースなどの手段で対外的にPRすることで、自社のブランディングが可能です。また先進的な環境活動がメディアに取り上げられ、企業の知名度・認知度が向上するケースもあります。
顧客からの問い合わせの増加や、新たなビジネスパートナーの獲得など、脱炭素経営を通じて事業成長のチャンスにつながります。
人材採用につながる
3つ目のメリットは、脱炭素経営に取り組む先進的な企業というイメージから、人材採用の強化につながるという点です。
環境問題への関心の高まりから、労働市場では「環境活動に積極的な企業に就職したい」「サステナブルな事業に従事したい」というニーズが増えています。脱炭素経営を通じて人材獲得競争で優位に立ち、人手不足の解消や優秀な人材の獲得などの効果が期待できます。
補助金を活用できる
4つ目のメリットは、脱炭素経営に関わるさまざまな補助金を活用し、事業コストを軽減できるという点です。
環境省は、カーボンニュートラルなどの環境活動に取り組む中小企業を対象とした補助事業を行っています[3]。例えば、設備投資(節電・省エネ設備など)に関する補助事業だけでも、IT導入補助金、SHIFT事業(工場・事業場における脱炭素化取組推進事業)、ものづくり補助金、省エネ補助金、ZEB補助事業(建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業)、脱炭素ビルリノベ事業(業務用建築物の脱炭素改修加速化事業)など、さまざまな制度を利用可能です。
中小企業はこうした補助事業を申し込むことで、コストを抑えながら脱炭素経営を推進することが可能です。
[3]経済産業省・環境省「中小企業等のカーボンニュートラル支援策」
4ステップで脱炭素経営の流れを解説
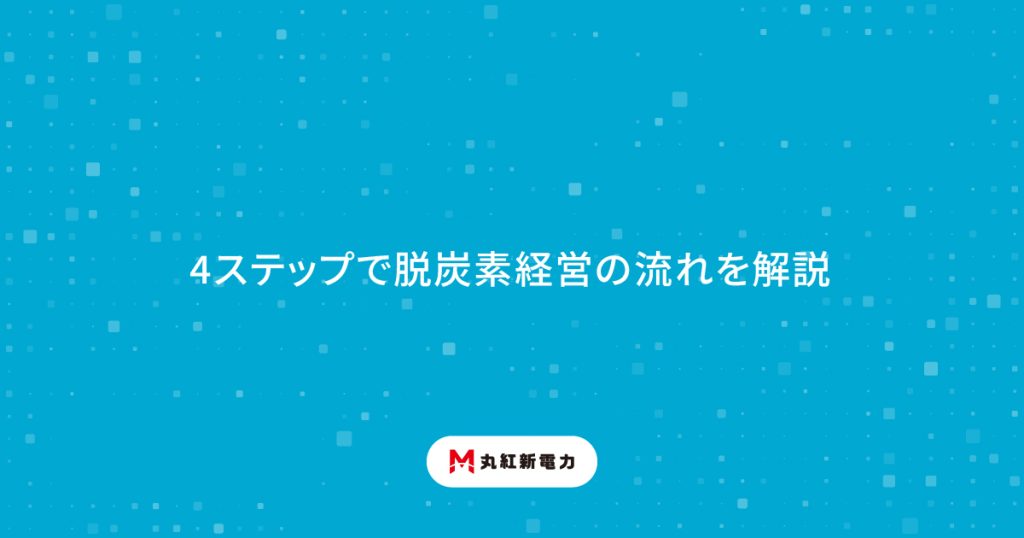
環境省はこれから脱炭素経営を始める方を対象として、「中小規模事業者向けの脱炭素経営導入ハンドブック」を作成しています。
ここでは、環境省のハンドブックに基づいて、脱炭素経営の流れを4つのステップで解説します。
- 情報収集
- CO2排出量の算定
- 削減計画の策定
- 計画の実行と見直し
情報収集
まずは政府の2050年カーボンニュートラル宣言など、脱炭素経営に関連した情報を収集し、政府や自治体、地域、業界、消費者の間で、どのような動きがあるかを調べましょう。環境問題についての理解を深められるとともに、中長期的な事業環境の変化を見通す上でも役立ちます。
その上で自社の経営方針や経営理念を踏まえつつ、脱炭素経営の方向性を検討しましょう。
CO2排出量の算定
脱炭素経営の目標の一つはカーボンニュートラルです。カーボンニュートラルを実現するには、二酸化炭素(CO2)の排出量と吸収量を均衡させ、事業活動から排出されるCO2を実質的にゼロにする必要があります。
自社のCO2排出量を実際に算定してみて、カーボンニュートラルに向けてどのような取組みが必要かを考えてみましょう。なお、CO2排出量は以下の計算式で求められます[2]。
- 活動量×係数=CO2排出量
※活動量とは、使用量や焼却量など、排出活動の規模を表す指標のこと
※係数とは、活動量当たりのCO2排出量のことで、環境省のホームページで確認できる
削減計画の策定
次にCO2排出量の削減計画を立てましょう。
カーボンニュートラルを効果的に推進するには、まず削減ターゲットを決めることが大切です。CO2排出量を事業所単位や事業活動単位で見える化し、排出量が多いものから優先的に削減対策を検討しましょう。
その後、CO2の排出源(設備や機器など)を洗い出し、実施可能な削減対策を個別に実施していきます。
計画の実行と見直し
最後に、削減計画の実行と見直しを行いましょう。
政府や中小企業向けSBT、業界団体などが設定している目標を参考にしつつ、削減対策のKPIを立て、目標に対しどの程度うまくいったか効果測定を行ってください[2]。
| 政府 | 2030年に2013年度比で46%の削減 |
| 中小企業向けSBT | 基準年(2018~2021年)に対して4.2%/年の削減 |
| 業界団体 (例:全日本トラック協会) | 2030年までにCO2排出原単位を31%削減 |
【まとめ】中小企業だからこそ経営に脱炭素の視点を取り入れよう
脱炭素経営とは、企業経営に脱炭素の視点を取り入れ、全社を挙げてカーボンニュートラルなどの環境活動に取り組む考え方です。脱炭素経営にはビジネス面でのメリットも大きく、競合他社に対する優位性の構築や、企業の知名度・認知度の向上、人材採用の強化など、事業成長へのチャンスとしての側面もあります。
脱炭素経営は、多くの企業が取り組む重要な経営課題ですが、中小企業にとっても大きくメリットをもたらす取り組みと言えます。環境省の「中小規模事業者向けの脱炭素経営導入ハンドブック」などを参考にしながら、4つのステップで脱炭素経営を進めていきましょう。














