容量市場とは?導入の背景や仕組みを詳しく紹介|電力供給の新たな枠組み
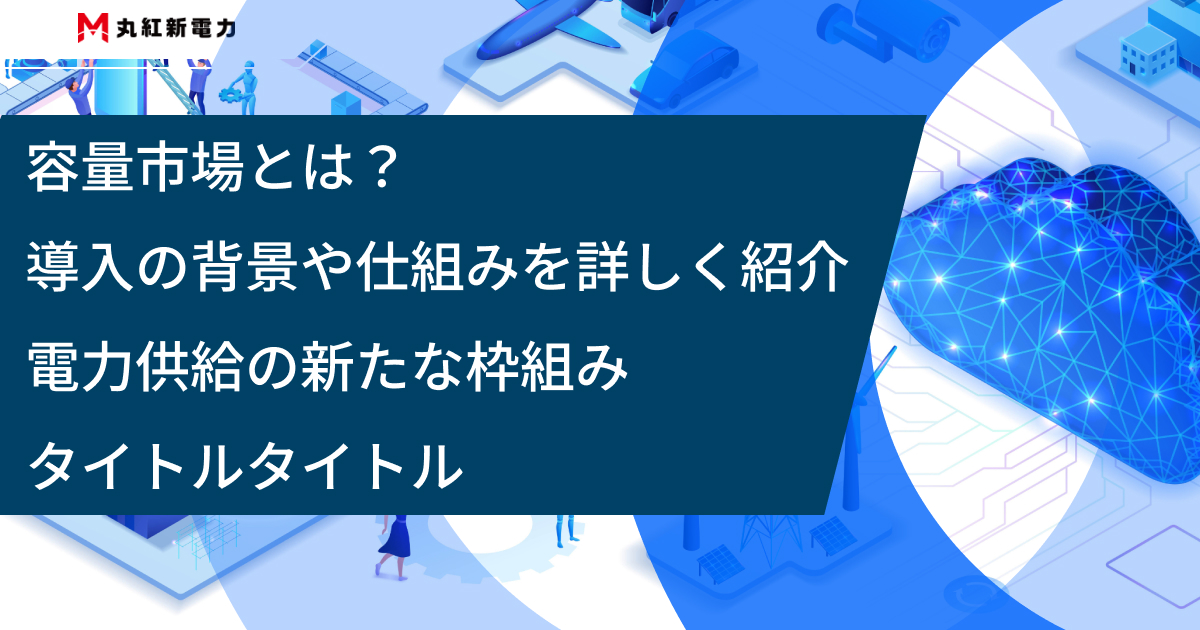
電力業界は、再生可能エネルギーの急速な導入や市場の変動により、従来の電力供給モデルでは対応が難しくなっています。特に、太陽光や風力などの再生可能エネルギーは自然条件に左右されやすく、安定した電力供給を維持するためには新たな仕組みが求められています。こうした背景の中で注目されているのが「容量市場」です。本コラムでは、容量市場の基本的な概念から導入の背景、その仕組みやメリット・デメリットまでを詳しく解説します。容量市場が電力供給に与える影響と今後の展望について理解を深めましょう。
[1]経済産業省 資源エネルギー庁「くわしく知りたい!4年後の未来の電力を取引する「容量市場」」
[2]電力広域的運営推進機関「容量市場かいせつスペシャルサイト」
>> 【法人のお客様向け】高圧・特別高圧の電力プランはこちら
目次
容量市場とは?

容量市場は、将来の電力需要に対応するために必要な発電能力(kW)を取引する市場です。この市場は、従来の卸電力市場が実際に発電された電力量(kWh)を取引するのに対し、発電可能な供給力そのものを取引対象としています。以下では、容量市場の基本的な概念と導入の背景について詳しく説明します。
容量市場の基本概念
容量市場とは、将来の電力需要に対応するために必要な発電能力(kW)を取引する市場のことです。従来の卸電力市場では、実際に発電された電力量(kWh)を取引しますが、容量市場では発電可能な供給力そのものを取引対象とします。これにより、発電事業者は安定的な収入を確保し、長期的な設備投資の予見性を高めることができます。容量市場は、電力供給の安定性を確保するために不可欠な仕組みとして、特に再生可能エネルギーの普及が進む現代において重要性を増しています。
容量市場導入の背景
容量市場の導入背景には、いくつかの要因があります。まず、再生可能エネルギーの急速な導入が挙げられます。太陽光や風力などの再生可能エネルギーは自然条件に依存するため、出力が不安定で予測が難しいという特徴があります。このため、電力供給の安定性を維持するためには、予備的な電力供給能力が必要となります。
また、従来のフィードインタリフ(FIT)制度により、再生可能エネルギーの導入が促進されましたが、同時に電源投資の予見性が低下し、将来の電力供給能力の維持が困難になる懸念が高まりました。さらに、電力需要の増加や電力市場の自由化に伴い、供給側と需要側のバランスを保つことが難しくなっています。これらの課題に対処するため、電力の供給能力(kW価値)をkWh価値から切り離し、別途取引する場を設けることで、発電事業者の投資意欲を喚起し、電力供給の安定化を図る狙いがあります。
容量市場の仕組み

容量市場の仕組みは、供給側と需要側の取引を通じて電力供給の安定性を確保するためのものです。このセクションでは、容量市場における取引の概要と容量オークションのプロセスについて詳しく説明します。
取引の概要
容量市場では、発電事業者を含めた供給力(kW価値)提供者が、電力広域的運営推進機関(広域機関)に対して発電容量を提供します。広域機関は、将来の電力需要増加や電力供給の不安定性に備えて、必要な容量を確保するために容量市場を通じて供給力を購入します。
具体的には、供給力提供者は自社が提供できる最大発電能力を申告し、これに基づいてオークション価格が決定されます。広域機関は、将来の需要予測に基づいて必要な容量を購入し、供給側はその対価として安定した収入を得ることができます。この仕組みにより、供給側と需要側双方にとってメリットが生まれ、全体の電力供給の安定性が向上します。
以下の表に、容量市場における供給力提供者と広域機関の役割と特徴をまとめます。
| 役割 | 供給力提供者(売り手) | 広域機関(買い手) |
|---|---|---|
| 主な主体 | 発電事業者を含めた供給力提供者 | 電力広域的運営推進機関 |
| 提供内容 | 発電容量(kW価値) | 必要容量の確保 |
| 目的 | 安定した収入の確保、設備投資の予見性向上 | 電力供給の安定化、地域全体の需要と供給のバランス維持 |
| メリット | 長期的な収入源の確保、投資促進 | 信頼性の高い電力供給の維持、需給バランスの最適化 |
容量オークションのプロセス
容量オークションは、需要側が必要とする容量を予測し、それに基づいて発電事業者が供給可能な容量を応募するプロセスです。オークションでは、価格が低い順に落札され、必要な容量が確保されます。この際、市場管理者は適切な競争を促進し、公正な価格形成を図ります。
例えば、2020年7月には初回オークションが実施され、2024年度分のkW価値の取引が行われました。この初回オークションでは、多くの発電事業者が参加し、供給力の確保に成功しました。しかし、初回オークションの結果を踏まえて、制度の改善点が浮き彫りとなり、供給力の管理や価格の妥当性、カーボンニュートラルとの整合性などを考慮した制度の見直しが行われました。これにより、容量市場の運営がより効率的かつ公平に行われるよう改善が図られています。
容量市場のメリット

容量市場には、電力供給の安定化や発電事業者の投資予見性向上、再生可能エネルギーの促進など、様々なメリットがあります。このセクションでは、それぞれのメリットについて詳しく説明します。
電力供給の安定化
容量市場の最大のメリットは、将来の電力供給能力を確保することで電力供給の安定化を実現できる点です。発電事業者は安定した収入を得ることで、発電設備の新設やリプレースを計画的に進めることが可能になります。これにより、需要ピーク時や予期せぬ供給不足時においても、電力の安定供給を維持することができます。
例えば、極端な気象条件や自然災害が発生した場合でも、容量市場を通じて確保された供給力があれば、電力網の安定性が保たれ、大規模な停電を防ぐことができます。また、企業や産業界にとっても安定した電力供給は生産活動の継続に不可欠であり、経済活動の円滑な運営に寄与します。
発電事業者の投資予見性向上
kW価値を別途取引することで、発電事業者は長期的な収入を見込めるため、設備投資の予見性が向上します。これにより、新たな発電所の建設や既存設備の維持管理が促進され、電力供給の能力が強化されます。発電事業者は安定した収入基盤を持つことで、リスクを低減しつつ積極的な投資を行うことができます。
例えば、新規の再生可能エネルギー施設を建設する際には、初期投資が大きくなるため、資金調達が困難になることがあります。しかし、容量市場を通じて確保された将来的な収入が見込めることで、金融機関からの融資が受けやすくなり、結果として新たな発電能力の拡充につながります。
再生可能エネルギーの促進
再生可能エネルギーは出力が不安定なため、調整可能な供給力が必要です。容量市場を通じて、必要なときに発電できる能力を確保することで、再生可能エネルギーの導入がさらに促進され、電源構成の多様化が進みます。これにより、環境負荷の低減やエネルギー自給率の向上が期待されます。
具体的には、例えば風力発電が強い日には発電量が増加しますが、需要が低い場合には余剰電力が生じる可能性があります。容量市場を通じて調整可能な供給力を確保することで、こうした余剰電力の調整や不足時の補完が容易になり、再生可能エネルギーの安定供給が実現します。これにより、化石燃料に依存しない持続可能なエネルギーシステムの構築が可能となります。
容量市場のデメリット

容量市場の導入により、小売電気事業者は容量拠出金を支払う義務が生じます。この拠出金を電気料金に反映する小売電気事業者もいるため、最終的な需要家にとっては電気料金の増加要因となります。具体的には、2024年から一部の小売電気事業者で容量拠出金による値上げが既に実施されており、需要家への負担が懸念されています。
例えば、電気料金が数パーセント程度上昇することで、家庭の電気代や企業の運営コストに影響を与える可能性があります。特に、中小企業や低所得層にとっては経済的な負担が大きくなるため、社会全体としてのバランスが求められます。
容量市場の現状と今後の展望

容量市場は導入以来、試行錯誤を経て運営が進められてきました。現在の状況と今後の展望について詳しく見ていきましょう。
初回オークションの結果と見直し
2020年7月に実施された初回オークションでは、予想以上の発電事業者からの参加が見られ、供給力の確保に成功しました。この初回オークションでは、特に再生可能エネルギーを積極的に導入する事業者が多く参加し、多様な供給力が確保されました。しかし、初回オークションの結果を踏まえて、供給力の管理や価格の妥当性、需給環境の変化に対応するための制度見直しが進められました。
具体的には、供給力の評価方法の見直し、オークションの運営プロセスの改善、そして透明性の向上が図られました。また、カーボンニュートラルとの整合性を高めるために、発電事業者のカーボンフットプリントを考慮した評価基準の導入も検討されています。これにより、容量市場が持続可能で公平な市場として機能することが期待されています。
調整力市場との連携
調整力市場の創設により、火力発電や揚水発電などの調整力を広域的に調達・運用することが可能となりました。市場原理による競争活性化を通じて、調整力コストの低減が図られ、電力供給の効率化が進んでいます。調整力市場は、容量市場と連携することで、より柔軟かつ効率的な電力供給体制を構築することができます。例えば、需要が急増した際や再生可能エネルギーの出力が低下した際には、調整力市場から迅速に調整力を調達することで、電力供給の安定性を維持することができます。これにより、電力システム全体の信頼性が向上し、消費者や企業にとっても安心して電力を利用できる環境が整います。
同時市場の検討
変動性再生可能エネルギーの更なる導入に伴い、調整力必要量や系統混雑の発生が増加すると予想されています。これに対応するため、供給力と調整力を同時に約定する「同時市場」の導入が検討されています。同時市場を導入することで、電力の供給と需要を同時に管理することが可能になり、これにより電力の安定供給と効率的な運用が期待できます。
同時市場では、発電事業者は自社の供給力と調整力を一括して提供することが求められます。これにより、各市場間での調整がスムーズに行われ、電力システム全体のバランスがより効率的に保たれるようになります。さらに、同時市場の導入により、複数の市場間での価格シグナルが統合され、発電事業者にとっての投資判断がより明確になります。
【まとめ】

容量市場は、将来の電力供給能力を確保し、電力供給の安定化を図るための重要な市場です。発電事業者にとっては安定した収入源となり、設備投資の予見性が向上します。また、再生可能エネルギーの導入促進にも寄与し、持続可能なエネルギーシステムの構築に貢献します。一方で、小売電気事業者や需要家には電気料金の増加といったデメリットも存在します。
今後、調整力市場や同時市場の導入により、容量市場は更なる進化を遂げると考えられます。電力供給の未来を見据え、容量市場の動向に注目し続けることが重要です。電力業界全体の持続可能な発展を支えるためにも、容量市場の理解と適切な対応が求められます。政策立案者や業界関係者は、容量市場を効果的に導入・運用することで、安定的かつ持続可能な電力供給体制の確立を目指すべきです。














