FIP制度とは?最新動向を踏まえたFITとの違い・メリット・デメリット徹底解説
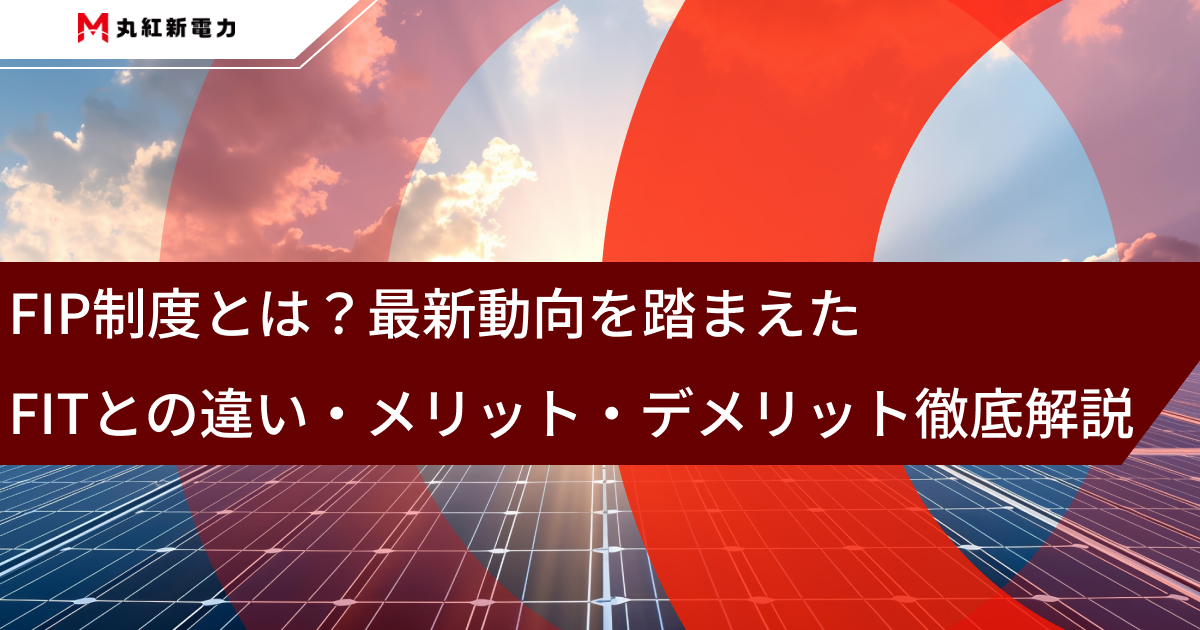
再生可能エネルギーの普及が世界的に進む中、日本でも再エネ発電事業者を支援する制度としてFIP(フィードインプレミアム)制度が注目を集めています。従来のFIT(固定価格買取制度)と比較して、FIP制度には様々な特徴や利点・欠点があります。本コラムでは、FIP制度の最新動向を踏まえつつ、FIT制度との違い、そしてそれぞれのメリット・デメリットについて詳しく解説します。再エネ投資を検討している法人の皆様にとって、有益な情報を提供しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
FIP制度とは?

制度の概要
フィードインプレミアム(FIP)制度は、再生可能エネルギーの発電事業者が市場の変動に柔軟に対応できるよう設計されています。従来の固定価格買取(FIT)制度に代わり、2022年から導入されたこの新しい支援策では、市場価格に加えて国からの追加支援を受けられるため、より競争力のある環境で事業を展開できます。具体的には、発電設備ごとに基準価格が設定され、市場価格との差額を国がプレミアムとして補填します。これにより、発電事業者は電力を市場で売却する柔軟性を持ちながら、追加の収入を得ることが可能となります。この制度は、再生可能エネルギーの競争力を高め、市場原理を活用した効率的なエネルギー供給を目指しています。
最新の動向
2023年以降、FIP制度は再生可能エネルギーの自立化を目指す政策の一環として注目されており、制度の拡充が進められています。特に、地域に根ざした再生可能エネルギーの地産地消を推進するための支援策や、蓄電池の活用による供給シフトなどが強化されています。また、認定基準の見直しや新規事業者への支援も行われており、FIP制度の普及が期待されています。最新の政策では、再生可能エネルギーの導入促進と同時に、電力システムの安定化を図るための技術革新も推進されています。
FIP制度とFIT制度の違い

買取価格の設定方法
| 項目 | FIP制度 | FIT制度 |
| 買取価格 | 市場価格に連動し変動 | 固定価格で長期にわたり保証 |
| 設定基準 | 発電設備ごとの基準価格設定 | 経済産業大臣が年度ごとに決定 |
| 収益の予測可能性 | 市場価格に依存し不確実 | 固定価格のため予測が容易 |
FIP制度では、買取価格が市場価格に連動するため、需要と供給の状況に応じて価格が変動します。一方、FIT制度では固定価格で買い取ることが保証されているため、収益の予測が容易です。FIP制度は市場のダイナミズムを反映する一方で、FIT制度は安定した収入を提供する点で異なります。
インバランスの取り扱い
| 項目 | FIP制度 | FIT制度 |
| インバランス対応 | インバランス料金が発生し、手当も含む | インバランス料金の免除特例あり |
| リスク管理 | 発電量の調整が必要 | インバランスリスクが低い |
FIP制度では、発電量の計画と実績の差異によりインバランス料金が発生する一方で、FIT制度では一定の条件下でインバランス料金の免除が可能です。これにより、FIP制度では発電事業者が市場価格変動およびインバランスリスクの管理により注意を払う必要があります。
非化石価値の帰属
| 項目 | FIP制度 | FIT制度 |
| 非化石価値の帰属 | 発電事業者に帰属し取引可能 | 国家に帰属し取引不可 |
| 取引の柔軟性 | 再エネ証書を通じて市場で環境価値を取引 | 環境価値は全需要家に分配される |
FIP制度では、非化石価値が発電事業者に帰属するため、再エネ証書を通じて独自に取引することが可能です。一方、FIT制度では環境価値が国に帰属し、取引の柔軟性が制限されています。これにより、FIP制度は発電事業者にとって追加の収益機会を提供し、環境価値の市場化を促進します。
▶下記記事も併せてご確認ください。
・企業向け非化石証書活用ガイド|持続可能なエネルギー戦略と最新市場動向
・トラッキング付き非化石証書の仕組みやメリットについて詳しく解説
FIP制度のメリット

収入の拡大余地
FIP制度では、発電事業者が市場価格に基づいた売電を行うことで、需要が高まり価格が上昇するタイミングを活用できます。特に、ピーク時や需給バランスが良好な時期に売電することで、収益性を高めることが可能です。また、発電事業者は市場の動向に応じて売電戦略を柔軟に調整できるため、収入の拡大余地が広がります。
電力システムのコスト削減
市場価格に連動した売電が促進されることで、需要と供給のバランスが取りやすくなり、電力システム全体の調整コストが削減されます。これにより、再エネ賦課金等の国民負担も軽減される可能性があります。さらに、効率的な電力供給が実現されることで、エネルギーの無駄遣いが減少し、全体的なコストパフォーマンスが向上します。
再エネと関連市場の拡大
FIP制度は再生可能エネルギーの柔軟な取引を可能にするため、蓄電池やエネルギーマネジメントシステム(EMS)などの関連市場の拡大を促進します。これらの技術は、変動が大きい再生可能エネルギーの効率的な利用を可能にし、エネルギー供給の安定性を高めるために不可欠です。さらに、FIP制度は地域に密着した再エネプロジェクトの推進にも寄与し、地産地消の実現につながります。これにより、地域経済の活性化や新たなビジネスチャンスの創出が期待されます。
FIP制度のデメリット

収入の不確実性
FIP制度のデメリットは、市場価格の変動による収入の不確実性です。特に市場価格が低迷する時期には、発電事業者が受け取るプレミアムも減少するため、予想よりも低い収益を得るリスクが生じます。これは、特に長期的な投資計画や運営コストの見積もりにおいて、計画の不確実性を高める要因となり得ます。そのため、発電事業者は、市場価格の変動リスクを適切に管理し、収益の安定化を図る戦略を検討する必要があります。また、長期的な収入予測が難しい点は、投資判断の際の大きな課題となります。この不確実性は、特に初期投資が多額となる再エネプロジェクトにおいて、資金調達の難易度を高める要因となり得ます。
しかし、最近ではこの不確実性を緩和するために、FIP制度を活用しながら需要家と長期PPA(電力購入契約)を締結する事例が増えてきています。長期PPA契約を通じて、発電事業者は需要家への安定的な再エネ供給を約束するとともに、契約期間中の売電価格を固定化することが可能となります。これにより、市場価格の変動に左右されずに一定の収入を確保でき、収益の予見性が向上します。
このように、FIP制度における収入の不確実性は大きな課題ですが、長期PPAのような戦略的な取り組みにより、そのリスクを緩和し、より安定した事業運営を実現する道が開けています。
▶下記記事も併せてご確認ください。
・コーポレートPPAとは?メリットや注意点を詳しく紹介
発電事業者への負担増
IP制度では、インバランス対応や発電計画の調整が求められるため、発電事業者にとっては運営負担が増加します。特に、中小規模の発電事業者にとっては、設備投資や調整能力の強化が経営を圧迫する要因となる可能性があります。また、市場価格の変動に対応するための技術的な対応や人材の確保も必要となり、運営コストが増加する傾向があります。
最近ではこれらの負担を軽減するためのソリューションとして、再生可能エネルギーなどの変動電源を束ねてインバランス対応や発電計画の調整等の業務を担うアグリゲーター(集約業者)の存在が注目されています。アグリゲーターは複数の発電事業者からの電力供給を統合し、効率的な需給バランスの管理や最適な発電計画の策定を行います。これにより、個々の発電事業者は複雑な調整業務をアグリゲーターに委託することが可能となり、運営負担を大幅に軽減できます。具体的には、アグリゲーターはAIやIoT技術を活用してリアルタイムで発電量と需要量を監視・分析し、迅速な調整を実現します。これにより、発電事業者は発電に専念できる環境が整い、効率的な運営が可能になります。また、アグリゲーターが提供するサービスを利用することで、小規模な発電事業者でも高度な調整能力を手軽に利用でき、競争力の向上につながります。
▶下記記事も併せてご確認ください。
・企業向けアグリゲーター活用術:分散型電源でエネルギー管理とレジリエンスを強化
認定プロセスの複雑さ
FIP制度の認定プロセスは、発電設備の基準適合性の確認や申請手続きの煩雑さにより、時間を要することがあり、新規事業者の市場参入の障壁になる可能性があります。特に、専門知識を持たない事業者にとっては、申請手続きや基準適合のためのコストが大きな負担となり得ます。
最新動向と今後の展望

政策の強化と支援策
政府はFIP制度を通じて再生可能エネルギーの自立化を推進しており、今後も制度の拡充や支援策の強化が期待されています。具体的には、認定基準の緩和や支援金の増額、技術革新への補助金の提供などが検討されています。また、FIP制度と他のエネルギー政策との連携を強化し、統合的なエネルギー戦略の一環として位置付ける動きも進んでいます。
地域活用の推進
地域ごとの再生可能エネルギー資源を活用した地産地消プロジェクトが増加しており、FIP制度はこれらのプロジェクトを支援する重要な役割を担っています。例えば、地域の風力や太陽光資源を活用した発電プロジェクトが増えることで、地域経済の活性化や雇用創出に繋がります。また、地域特性に合わせたエネルギーミックスの最適化が進むことで、エネルギーの安定供給も実現されます。
FIP制度の拡大と持続可能性
FIP制度は、再生可能エネルギーの大量導入と持続可能な運営を目指すために、今後さらに拡大していく見込みです。特に、蓄電池の導入やスマートグリッド技術の活用が進むことで、FIP制度の持続可能性が高まり、再エネの安定供給が期待されます。これにより、脱炭素社会の実現に向けた重要なステップとなるでしょう。
まとめ

FIP制度は、柔軟な再生可能エネルギー支援策として、事業者に収入の拡大余地を提供し、電力システムのコスト削減や関連市場の拡大に寄与しています。一方で、市場価格に依存する収入の不確実性や発電事業者への負担増、認定プロセスの複雑さといったデメリットも存在します。しかし、最新の政策強化や地域活用の推進により、FIP制度は今後ますます重要な役割を果たすことが予想されます。法人向けにFIP制度とFIT制度の違いや自社の事業に最適な制度を慎重に検討することが求められます。再生可能エネルギーへの投資を検討している企業にとって、FIP制度の理解は欠かせません。メリット・デメリットを最新の動向を踏まえた上で、最適なエネルギー戦略を立案しましょう。














